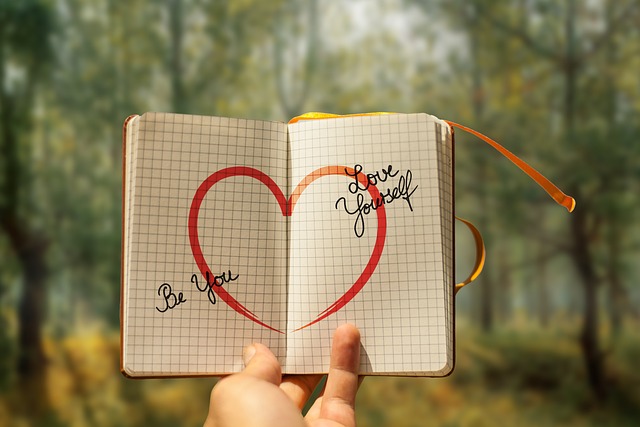私たちは日々、いろんなことを「自分の意志」で選んでいるつもりです。
仕事、恋愛、家庭、人間関係──
でもふと立ち止まって考えると、こんな疑問が浮かぶことはありませんか?「そもそも、私が“正しい”と思ってるこの価値観って、どこから来たんだろう?」
実は心理学の中には、こうした“当たり前”や“常識”に問いを投げかける視点があります。
それが 社会構成主義(Social Constructionism) です。
■ 心理学でいう“現実”は、案外あいまい
私たちはつい、
「現実はそこにただ存在している」
「人の性格は生まれつき決まってる」
「男はこう、女はこう」
と信じがちです。
でも社会構成主義はこう言います。
「現実は、“人と人の関わり”の中で意味づけされたもの。
つまり、“会話”や“文化”の中で、作られてきたんです」
これは、心理学における“認知”や“アイデンティティ”の成り立ちにも通じています。
■ 「人は環境によってつくられる」その“環境”が社会的な対話だった
たとえば、ある人が「自分はダメな人間だ」と思っているとします。
その人にとっては“現実”でも、
実はそれは過去に言われた言葉や、
繰り返し触れてきた社会的なメッセージの積み重ねかもしれません。
- 「男のくせに泣くな」と言われた経験、「女の子だからおとなしく」と言われた経験
- 成績や成果で評価される経験ばかりだった子ども時代
- SNSで“成功者”ばかり目にする毎日
こうした環境との“対話”の中で、
人は自分の価値や意味を形づくっていく。
これが社会構成主義の基本的な考え方です。
■ 自分を変えるには、「物語」を書き換えることから
心理療法の世界でも、この視点はよく使われます。
たとえばナラティブ・セラピーでは、
「クライアントの語る“自分の物語”が、今の現実を作っている」と考えます。
そしてその物語に新しい視点を加えることで、
人は自分を違う形で理解し直し、変化していけるのです。
社会構成主義は、
「現実は一つではない」
「意味づけは変えられる」
という、とても柔軟で人にやさしい前提を持っています。
■ 心の“自由”を取り戻す
「ちゃんとしなきゃ」
「もっと成果を出さなきゃ」
「人に嫌われたくない」
そう思ってしまう時、それは「あなた自身の声」ではなく、
社会の中で知らず知らずに吸い込んできた“物語”かもしれません。
社会構成主義の視点を持つと、こうした“思い込み”から少し距離を取ることができます。
「これは本当に“自分の考え”なのか?」
「誰かの声を、自分の声と勘違いしていないか?」
そんなふうに問い直すことができたら、
今までよりも少し、自由になるかもしれません。
心理学的な視点で社会構成主義を捉えると、
それは「現実を疑うための道具」ではなく、
“自分をやさしく問い直す”ためのまなざし、視点を増やすこと、になります。