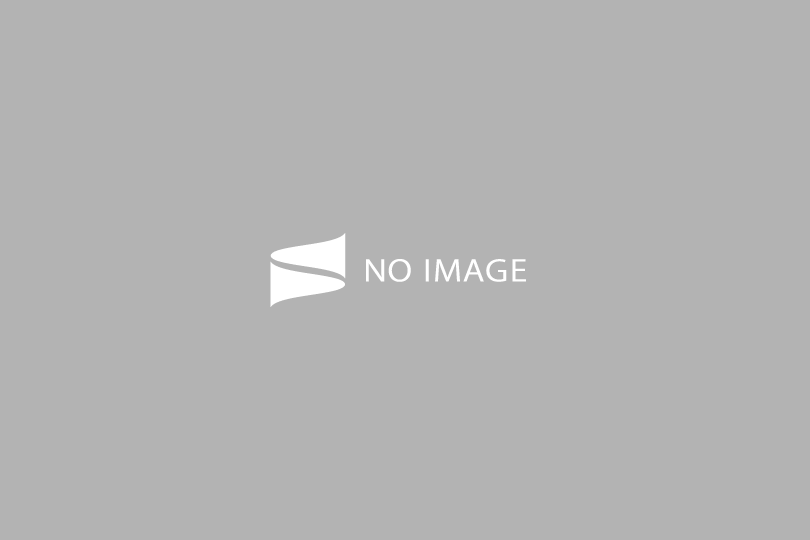読んで感じたのは、「実はミニマリストの考え方にも通じる」ということ。
この本で語られている“マーケット感覚”とは、次の4つの力を鍛えることだと感じた。
① 相場や値札ではなく、「自分の独自基準価格」を考える癖・能力をつけること。
ミニマリストのように、「世間的に良い、売れてる」とされているという理由だけではなく、自分が何に価値を感じ、いくらなら妥当だと思うかを考える癖をつける。
相場や値札は、誰かが決めた“他人の判断の結果”にすぎない。
それに振り回されず、まず「自分にとってこの商品はいくらの価値があるのか」を考えること。
自分独自の考え方が身についていないと、値札――つまり他人がつけた評価――がないものは、すべて「価値がない」と思い込んでしまう。
たとえば、「今、雇ってもらえていない」=「今、自分の労働力には値札がついていない」=「だから自分には価値がない」と考えてしまうように。
② 人が動く仕組み、理由、モチベーションのシステムを理解すること。
「どういう人が、なぜお金を払うのか」「どんな動機でそれを求めるのか」といった“他者の視点”を持ち、
他人が動く理由や市場の構造を読み解く癖をつける。
そして、そのためには、自分の本当の欲望に素直になることがまず大事だ、と著者は言う。
自分の欲望に対して、盲目的に「我慢」とするよりも、
「自分は何が不満なのか」→「自分が求めている理想はどんな状態なのか」→「自分が本当にほしいものは何なのか」と問いを重ねていくほうが、ずっと建設的だ。
自分の欲しい何かに蓋をしていて、他人の心やモチベーションは分からない。
③ 「組織ではなく、市場に評価されるスキル」を学ぶこと。
組織の偉い誰かの判断→実行、ではなく、自分でとりあえず実践する。
その結果得られたフィードバックをもとに、学び、改善していく。
④ 「失敗と成功の関係性」を理解する。
失敗は成功の反対概念ではなく、成功までのプロセスの一部。
テニスでいえば、スクールでフォームを習っても、試合に出たら全く勝てない、という経験のようなもの。
とりあえず実践に出て、フィードバックを受け、修正していけばいい。
「失敗しないように」と準備ばかりしていては、いつまでもスタートできない。
つまり、マーケット感覚とは「自分の価値を自分で決める力」であり、
「他人や社会が動く仕組みを読み解く知性」であり、
「実践の中で、フィードバックをポジティブに変換して、自分をアップデートしていく柔軟さ」でもある。
この4つを身につけることができれば、
“誰かに選ばれる”のではなく、“自分で市場を選び、価値を生み出す”生き方ができるのだと思う。