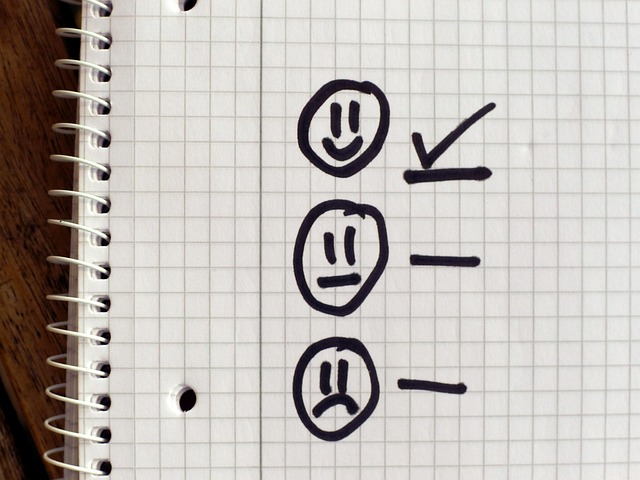① 何を「残すか」を選ぶ=自分の基準を問う行為だから
- 「これは何で必要?」
- 「今の私に合ってる?」
- 「本当に好き?」
こうした問いを繰り返すことで、親や社会やパートナーの他人基準ではなく
自分なりの判断基準=“選ぶ軸”が育つんです。
② 「迷う」を繰り返すことで、決断力がつく
- 最初は悩んでも、だんだんと「即決できる」ようになる
- 「これは必要、これはいらない」とスッキリ区別できるようになる
つまり、判断のスピードと精度が上がる=選ぶ力の成長!
③ 「今の自分」を意識するようになる
- 「昔は気に入ってたけど、今は着てない」
→ モノを通じて、自分の変化を感じられる
過去の自分ではなく、「今の自分」に合うものを選ぶ習慣がつくようになる
④ 「手放しても大丈夫」を体験することで、怖くなくなる
- 最初は勇気が必要だったけど、捨てたあとに「意外と平気だった」「スッキリした」と気づく
- その経験が、次の選択をラクにしてくれる
“選ぶこと=失うこと”ではないと体感することで、選ぶのが怖くなくなる
⑤ 選ぶことで、「自分にとって大切なもの」が明確になる
- 残したモノを見ると、「私ってこういうのが好きなんだな」とわかる
- モノだけじゃなく、人・予定・情報も選べるようになる
選ぶ力は、人生全体に応用できる土台の力になる