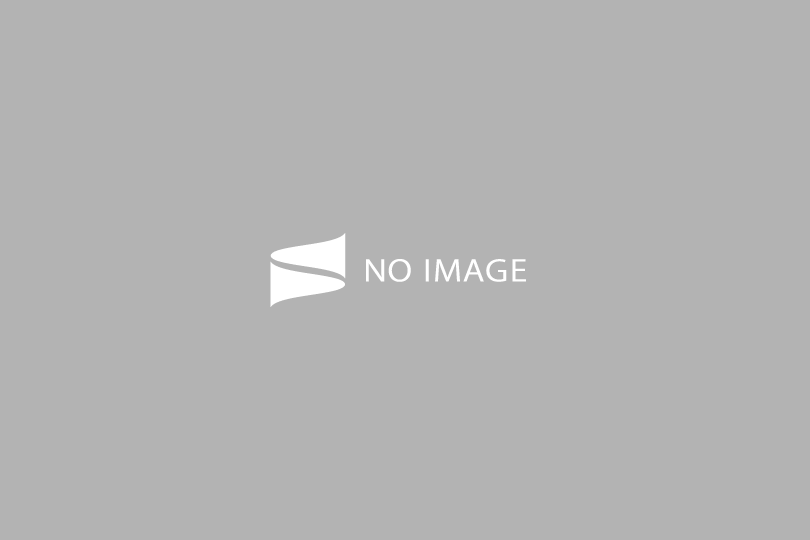2035,10年後のニッポン――堀江貴文『未来予測大全』を読んで
仕事、暮らし、産業、お金、経済、テクノロジーが社会をどう変えていくのか。そんなテーマで描かれた本の中で、私に自分事として最も刺さった問いは「満員電車はなぜ不滅なのか?」というものでした。
(もちろん、教師がちゃが無くなる、宇宙開発での日本のポジションや中国人による土地購入の話など、気になるトピックは沢山ありますが…)
テクノロジーの進歩によって、私たちは働き方を選べるようになりました。リモートワークやオンライン会議の普及で、もはや「毎朝、同じ時間に同じ電車で出勤すること」は絶対ではないはずですし、小池都知事が「満員電車ゼロ」を掲げても、現実は一向に変わっていません。
しかし、不満の声をあげる有権者がほとんどいない理由として、
著者は「実行力や行動力のある人は、政治を変えようとするのではなく、自分のライフスタイルを変えようとするからだ」と述べており、私も本当にその通りだと感じました。
満員電車はなぜ不滅なのか?
リモートワークが当たり前にできる時代。実際、コロナ禍では多くの人が在宅勤務を経験しました。
それでも満員電車が残り続ける理由はいくつかあります。
- 企業文化:日本では「出社=働いている証」という価値観が根強い。
- 人々の行動選択:「会社が言うから」と従う人が大多数。
- 都市構造:首都圏一極集中の仕組みが変わらない。
- 給与制度:多くの会社は固定給が前提で、出来高制ではない。
理屈の上ではリモートワークは時間効率も上がり、生産性も向上しそうです。
しかし実際には、上司や同僚、相互監視による同調圧力という緊張感にさらされた方が仕事がはかどる人が多く、生産性が上がるようで上がらないのが現実です。
出社が「良かった」と思っていた会社員時代
私自身、会社員の頃は「出社して顔を合わせて働く方がいい」と思っていました。
部下や上司と感情のすれ違いも防げるし、時には雑談を言い合えるのも大事。
自分がミスをしたとき、あるいは部下がミスをしたときにも、誰かと共有できることで問題が大きくなる前に対処できる。
そう考えると、出社の方が効率的だと感じていたのです。
けれど今振り返ると、それは仕事そのものに「やらされ感」があったからだと気づきました。
仕事とはそもそもつまらないもの、自分のためではなく、誰かに満足してもらうものだという感覚が根底にあり、だから、自分にとってつまらないことや、納得できないことにある程度耐えることが多くても仕方ない、というのが無意識にありました。
自分で仕事を選んでる訳ではなく、「与えられた仕事」をこなす日々。
そんな状況では、家でひとり黙々と働くのはつらく、人との会話に「仕事の意味」を見いだしていたのかもしれません。
自分で選べる働き方へ
会社員を辞め、個人事業主として主体的に働く今は違います。
好きではない仕事を無理にやる必要はなく、やらされ感は無く、愚痴で気持ちを埋め合わせる必要もない。だからこそ「出社」という形式にこだわらなくてもいいと感じています。
満員電車の不滅や出社強制の背景には、企業文化や給与制度が横たわっています。
けれど、突き詰めれば問題は「場所」ではなく、自分が仕事を選べるかどうかにあるのだと思います。
一方で少数派ですが、リモートワークによって生産性が上がる人もいます。彼らは今まで通勤に使っていた時間や体力を別の事に、趣味や家族との時間や趣味に打ち込む時間をつくったり、高水準のワークバランスを実現することができていている人もいるし、
今後この2極化は進む、と、著者は述べています。
2035年を見据えて
堀江氏の未来予測が描くように、テクノロジーはさらに進化し、AIや自動化が当たり前になるでしょう。
そうなれば、満員電車に象徴される「非効率な慣習」はますます違和感を増すはずですが、引き続き不滅ではあると思います。
そして最終的には、
リモートワークで自由度の高い働き方を選ぶか、
昔ながらの管理・拘束された働き方を選ぶか――どちらにするかは自分次第です。
2035年の未来をどう迎えるかは、社会の変化以上に、自分が働き方を選べるかどうかにかかっているのだと思います。