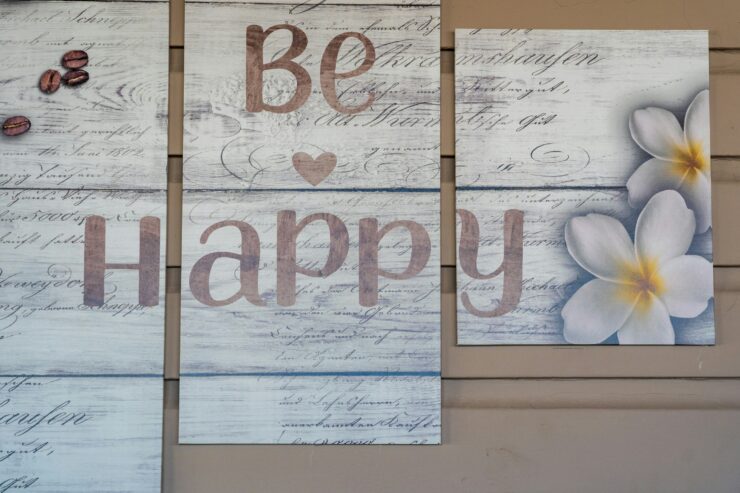地方に出かけて人と交流すると、その土地に根ざしたリアルな人間関係にふれることがあります。
訪れるのは、人口50万〜100万人ほどの中規模都市が多いのですが、そこでの人付き合いには、東京とはまた違った「濃さ」があると感じます。
長く続くつながり
長く同じ場所に住んでいる人が多いため、何十年も前に子どもが卒業した小学校のママ同士が、今もつながりを持っていたりします。
誰がどこに勤めているか、どの子がどこの学校に行ったか、親戚やご近所の話も自然と耳に入ってくる。
旅行に行けば、ご近所さんたちにお土産を買って帰るのも当たり前のように続いています。
人間関係の濃さのメリットとデメリット
こうした関係を「地続きで、じんわり温かい」と感じる人もいれば、「いつの間にか何でも筒抜けになっていて、少し面倒だな」と思う人もいるかもしれません。
安心感と引き換えに、距離の取りづらさもある。人間関係の濃さには、良し悪しの両面があります。
わかりやすい幸せの形
さらに、地方では「その土地に根ざした、わかりやすい幸せの形」が存在しているのだな、と感じることもあります。
ひとつの会社で長く勤め、その会社から通える範囲で結婚し、子どもを育て、お庭でバーベキューをしたり、野菜を育てたりできるような「マイホームを実家の近くに建てる」。
そんな暮らしのイメージが、実際に目の前にある。ある種の「定番」として根づいた幸せのスタイルが、ここにはまだしっかりと残っているのだなと思いました。
幸せについて考える機会
そして、そうした「わかりやすい幸せのカタチ」がある場所に住んでいて、たまたまその流れに自然と乗ることができた場合、「幸せとは何か」とあえて考えることなく、生活していけるのかもしれません。
日々の暮らしの中で、自分の在り方を深く問う機会は、もしかしたら少ないのかもしれません。
東京の人付き合い──断片的なつながり
一方で、東京での人付き合いは、また異なる形をしていると感じます。
東京では、人はたまたま近所に住んでいるからという理由でつながることは少なく、むしろ仕事や趣味、ジムなど、その土地ではなく、共通の目的や関心を共有する場で関係が生まれることが多いように思います。
その場その場の関係性
つまり、「どんな共通点、目的があるか」といった文脈によって、その場その場で異なる関係が構築されるのです。
その場では楽しく会話したり、一緒に仕事をしても、一歩外に出れば、相手がどんな生活をしているのか、どこにどんな家に住んでいるのか、案外分からないことも珍しくありません。
社会構成主義の視点から考える
社会構成主義の視点で考えれば、これは「関係性が、土地ではなく、その場のコンテクストに依存している」ということかもしれません。
人との関係は、その場に集まった目的や背景によって形作られ、そこから離れれば別の意味づけや関係性が生まれる。
そのため、東京の人間関係は断片的でありながら、その分、多様な選択肢や可能性が広がっているとも言えます。
自分の幸せを見つけることへの迷い
そして、そんな東京の暮らしでは、
出会う人々が目的ごとに変わり、多様な価値観に触れる中で、自分の「好き」や「心地よさ」「幸せに感じること」をきちんと言語化しておかないと、つい他人と比べてしまったり、正体の見えない焦りや疲れを感じてしまうこともあるのだと思います。
幸せのカタチが一つではないぶん、「自分にとっての幸せとは何か」を考え、迷う機会が自然と増えていきます。
環境と意思決定
私たちは日々、いろんなことを「自分の意志」で選んでいるつもりです。
仕事、恋愛、家庭、人間関係──
しかし、やはりどんな土地に生まれ育ったか、どこに住んでいるのか、その環境で人々との“対話”の中で、人は自分の価値や意味を形づくっていく。
環境や土地の文化、そこにいる人々との関係性が、自分の価値観や意思決定に少なからず影響を与えているのだと、改めて感じさせられました。