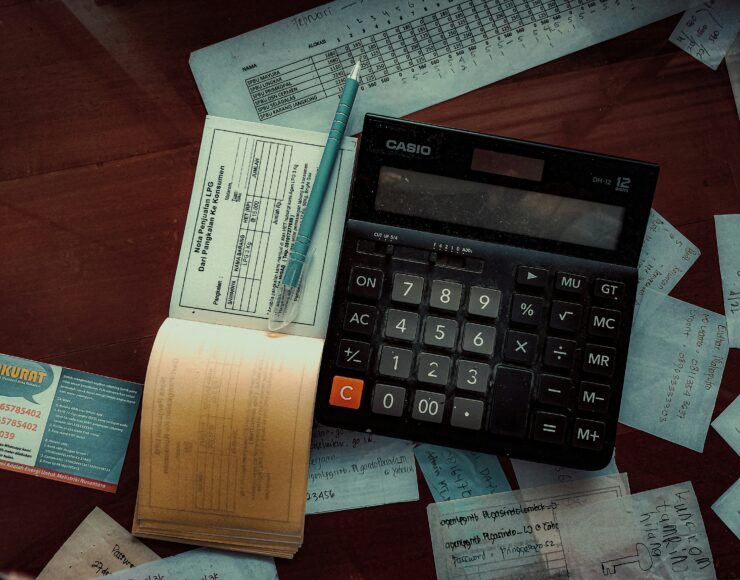四国に転勤で引っ越して、約1か月。
水が美味しい、野菜や魚が新鮮で美味しい、空が広くて青く、夜には月や星もよく見える――そんな日々の中で、生活の幸せ度、QOLは爆上がりです。
しかし、ひとつ驚いたことがありました。
光熱費が、東京にいたときのほぼ倍になったのです。
「なぜこんなに高いの?」――その疑問を(取り急ぎ電気代)調べてみました。
🔌 1.四国電力は原発を持っている
四国電力は**伊方原子力発電所(愛媛県)**を所有しています。
現在は3号機のみが稼働中(1・2号機は廃止)。
原発は燃料コストが安いため、稼働していれば電力コストを抑える効果があります。
しかし、1基しか稼働していないため、全体の電力供給に占める割合は限られています。
⚙️ 2.火力発電への依存度が高い
四国電力の電源構成(2024年度実績の目安):
- 火力:約70%
- 原子力:約15%
- 再エネ(水力・太陽光など):約15%
火力発電は、燃料(LNG・石炭・石油)の輸入コストが高く、円安や燃料価格上昇時にはコストが直撃します。
原発が1基しか動いていない今、原発コスト抑制効果は限定的です。
🏙 3.需要規模が小さく、スケールメリットが効きにくい
東京電力は首都圏(関東4000万人)という巨大な需要地を抱えていますが、四国電力の供給エリアは人口約350万人ほど。
電力会社の固定費(設備・人件費・送電網維持)は一定なので、需要が小さいと1kWhあたりのコストが割高になります。
これは地方電力会社が不利になる構造的な要因です。
🌏 4.太陽光発電の導入率が高く、再エネ賦課金が大きい
四国は日照時間が長く、太陽光発電の導入率が全国でも上位。
その分、再エネ賦課金として電気料金に上乗せされやすくなります。
(再エネ賦課金=太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取る際に要した費用を、電気の利用者全員で負担するための仕組み)
四国では、一般の住宅でも、太陽光パネルを備え付けているお宅を頻繁に見かけます。
💸 5.電力融通の自由度が低い
東京電力は広域電力取引市場や他地域(中部・東北など)との連系線が強く、安価な電力を融通し合うことができます。
四国は地理的に融通の経路が限られ、電力市場での調達コストも高めになりがちです。
生活実感と学び
ちょっと高めの光熱費も、こうした背景を理解すると納得感が増しました。
現在の自分個人の幸せだけを考えたら、QOLは確実に爆上がりです。
でも長期の視点で考えてみると、人口減少は、その個人の幸せを守ることを難しくしてしまう――ジワジワ効いてくる社会問題でもあるんだな、と実感しました。
また、どちらの電力会社も、火力発電用の燃料(LNG・石炭・石油)はほとんど輸入に頼っているので、円安や国際燃料価格の影響は受けます。
更に、原子力も、政策・規制・国際基準の影響を大きく受けますし、
安定的に安価な光熱費を享受できるって、色んな条件が整って実現できることだな、って今更ながら気づきました。