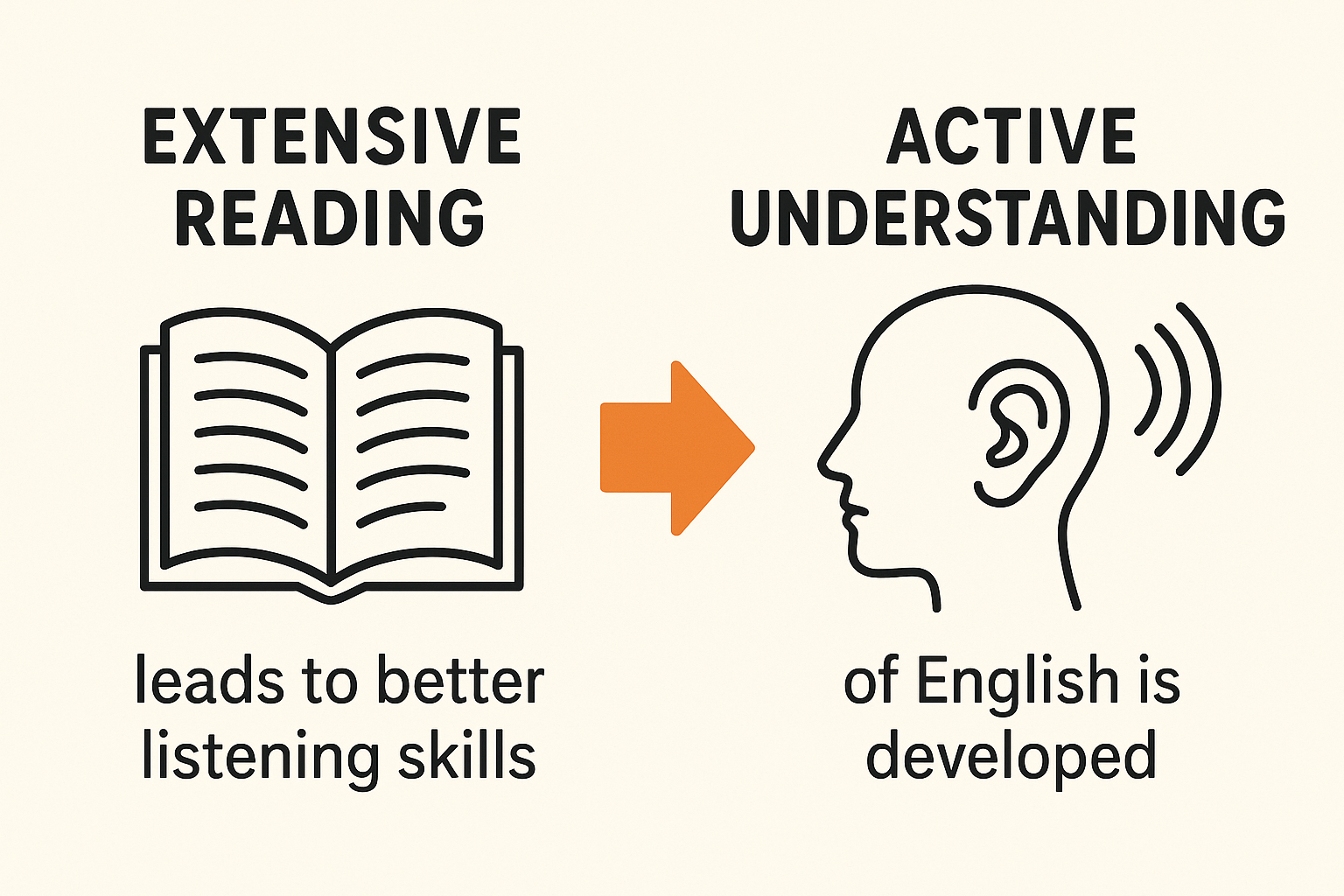英語を「能動的に理解する回路」が育つ
英語多読がリスニングに良いのは、**「英語を能動的に理解する回路」**が鍛えられるからです。
多読を続けるうちに、英語の「語順」や「リズム」に自然と慣れていきます。
日本語に訳さず、英語のまま意味を取るクセが身につき、読むスピードも上がってきます。
その結果、英語を英語のまま処理する脳の回路ができあがり、リスニングでも自然に働くようになります。
多読はスピーキングにも直結する
英語多読は、リスニングだけでなくスピーキング力にも直結しやすいと感じます。
理由は、読むことは、英語を能動的に推測しながら読み進めるトレーニングだからです。
単に聞いた音を真似るのではなく、自分で意味を組み立てる練習ができるため、英語を話すための「考える力」が育ちます。
一方、シャドーイングは、聞こえた音を忠実に再現することが中心です。
シャドーイングもとても優れた練習法ですが、受動的な要素がやや強いといえるでしょう。
もちろん、どちらが自分に合うかは英語レベルや目的によりますが、「英語を話す」という行為自体が能動的な活動である以上、多読の効果は非常に大きいと考えています。
また、本という正確な文法に触れているので、文法の迷いが減り、(例えば単数なのか複数なのか、三単現のS付けるかどうか、など)英語を話す時のストレスが減ります。
推測力がリスニングでも活きる
多読をしていると、知らない単語が出てきても、前後の文脈から推測する力が自然と身についていきます。
この推測力は、リスニング中にも生きてきます。
わからない単語があってもパニックにならず、全体の流れを追い続けることができるようになるのです。
そして、リスニングに余裕ができるので、スピーキングにも余裕が出ます。
読書家は話し上手。英語も同じ
日本語でも、読書家の人は語彙が豊富で、話し上手な人が多いですよね。
たくさんの言葉や表現に触れることで、自然に語彙力や表現力が磨かれ、それが話す力へとつながっています。
これは、英語でも同じことが言えます。
多読を通じて膨大な英語表現に触れ、語彙を増やし、英語らしいリズムや言い回しに慣れていく。
その積み重ねが、英語で話すときの「言葉を選ぶ力」や「伝える力」を支えてくれるのです。
英語を話すとは、能動的な作業
英語を話すことは、単なる音の真似ではありません。
自分の中にある言葉のストックを使い、状況に合わせて表現を組み立てる、非常に能動的な行為です。
だからこそ、多読で育まれる**「能動的な理解力」と「語彙力」**は、リスニングだけでなくスピーキング力の向上にも大きな役割を果たすのです。