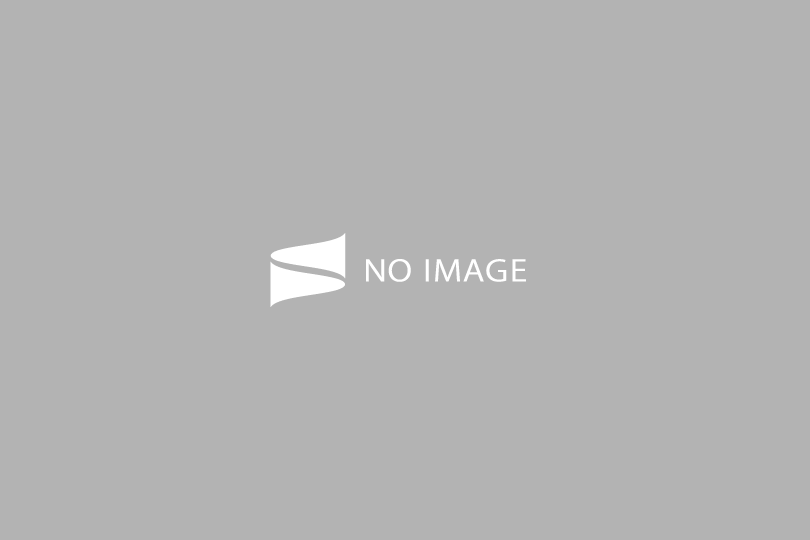☆こちらの本は、Audibleオーディブルで無料で試せます。
1. 一度きりの「死」に備えるということ
誰しも、できることなら安らかに死を迎えたいと思っているはずです。しかし、死は人生でたった一度きりの“本番”であり、練習もやり直しもできません。ならば、自分の死に備えるために、他の人の経験や例から学ぶことが、唯一できる準備ではないでしょうか。
2. 現代社会が「死」を遠ざけている
医療の進歩によって「死」は病院の中に押し込められ、私たちの目から遠ざけられています。かつては自宅で家族に看取られて亡くなるのが当たり前でしたが、今では死に立ち会う機会すら少なくなり、「死を語ること」そのものがタブー視されるようになっています。
3. 「生」だけを肯定し、「死」は否定される
その結果、「死」はどこか現実離れした、得体の知れない恐怖となってしまいました。そして私たちは、「死は絶対に避けるべきもの」という価値観に、無意識のうちに支配されているのかもしれません。
しかし、耐え難い苦痛だけが続いている状態で、治る見込みもほとんどない中でも、「頑張れ」「生きろ」と励ますことが、果たして唯一の正解なのでしょうか?
「生きること」が絶対的に善で、「死ぬこと」が絶対的に悪という前提で、私たちは思考停止してしまってはいないでしょうか。
4. 延命治療がもたらすもの
“助かるかもしれない”という希望があるからこそ、多くの人は病院に駆け込みます。しかし、その希望が叶わなかった場合、「助からないけれど、死ねない」という苦しい状況が待っています。延命治療によって、意識もなく、身動きもできず、チューブに繋がれたまま「生かされる」状態になるのです。
5. 両立しない“希望”と“拒否”
「少しでも助かるなら治療は受けたい。でも、悲惨な延命治療だけは嫌だ」——この願いは一見もっともらしく見えますが、実際には両立しないことが多いのです。治るかどうかは医師でも予測が難しく、「治るかもしれない」というわずかな可能性のために延命治療が選ばれてしまいます。
6. パプアニューギニアの医師の言葉
著者がパプアニューギニアで出会った現地のドクターの言葉にハッとさせられます。
「歯が抜け、目が見えなくなって、足が弱くなって歩けなくなったら、それは死ぬ時だ」
この言葉には、死を特別視せず、老いの延長線上にある“自然な終わり”として受け入れる感覚があります。
7. 老いと死を拒む日本の姿勢
日本人だったら、こんな風に考えるでしょうか?
歯が抜ければ入れ歯を入れ、白内障になれば人工レンズを入れ、足が弱ればリハビリに励む。
私たちは「老い」や「死」に向き合うのではなく、それらを拒み続ける選択ばかりしているのではないでしょうか。
8. 本当に「百年生きたい」のか?
人生百年時代が賞賛されていますが、本当にそうでしょうか?
百歳まで生きられるというより、百歳まで“死ねない”社会になってはいないでしょうか?
治らない病を抱えながら、何ひとつ楽しめないままチューブに繋がれている状態で、私たちはそれを“生きている”と言えるのでしょうか。
9. 「死を知ること」は「生を選ぶこと」
「死を知ること」は、「よりよく生きること」につながります。
そして、自分がどう死にたいかを考えることは、自分がどう生きたいかを考えることでもあるのです。